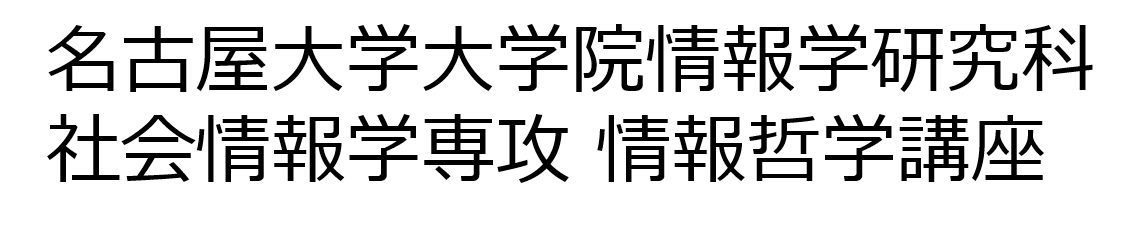本研究プロジェクトについて
少子高齢化が進展し労働力不足が懸念される中で、介護や育児をする必要がある人や高齢者など、様々な背景や価値観を有する人々が、自らのライフスタイルに応じて多様な活動に参画できるようにすることが重要です。そのためには、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現することが鍵となります。
ロボットやVRなどの技術によって実現するアバターはそれを可能にするツールになるはずです。その一方で、アバターは人間の生きる根本的な条件を変化させるため、その普及に際しては大きな倫理的・法的・社会的課題(ELSI)も存在します。そこで本研究プロジェクトではアバターが普及した社会の在り方をELSIの観点から探求し、様々な分野のステークホルダーと議論・対話をしながら、よりよいアバター共生社会の実現を目指していきます。
アバター共生社会の倫理 セミナー・シリーズ
本研究プロジェクトの一環として、様々な分野の専門家をお招きしてアバター倫理に関連する研究や取り組みをご紹介いただくセミナーを開催します。
「メディアコミュニケーションのリデザイン」講演会(第3回ReMediCom講演会)のお知らせ
本講演会「メディアコミュニケーションのリデザイン(ReMediCom)」では、新しいメディアの登場やコロナ禍の影響によってコミュニケーションが変化しつつある状況を踏まえて、自由で多様なコミュニケーションのあり方を探求してきました(*1)。
この度、ムーンショット型研究開発事業(目標1)で開発が進められる「サイバネティック・アバター」(*2)の可能性と課題について、歴史的視野の下で検討を行うために、西洋哲学史を専門とされる中畑正志先生と、情報技術史を専門とされる喜多千草先生を講師としてお招きし、ご講演いただきます。ご関心がおありの方はぜひご参加ください。
- 日時:2024年3月24日(日) 13時~17時
- 開催方法:現地会場とオンラインのハイブリッド
- 会場:キャンパスプラザ京都 6階 第8講習室(アクセス)
- 参加費:無料
- 参加申し込み:オンライン参加を希望される方は、2024年3月22日(金) 17:00までに、登録リンクにてお申し込みください。お申込みいただいた方には、後ほどメールにてZoomのログイン情報をお送りします。(現地会場での参加を希望される方は、事前申し込み不要です)
- プログラム(暫定):
- 13:30-13:45 趣旨説明(呉羽 真)
- 13:45-15:15 講演①:中畑 正志「In medias res ──媒介者としての「メディア」を歴史的に考える(仮)」
- 15:30-17:00 講演②:喜多 千草「疑似ローカル・同期のプレゼンスとしてのCA」
- 講演タイトルと要旨
- ①中畑 正志「In medias res ──媒介者としての「メディア」を歴史的に考える(仮)」
「メディアコミュニケーションのリデザイン」という全体的課題のもとで、「サイバネティック・アバター」をテーマとして、それを歴史的な視点から考えてみること。──これが私に与えられた役割である。アリストテレスのこのテキストはこちらの写本に従って読むべきではないか、といったことに頭を悩ましている私には、かなり遠い分野の話ではあるが、ここは素直に、私に可能な範囲でこの役割を果たすことにしたい。
「メディアコミュニケーションのリデザイン」という全体的課題と「サイバネティック・アバター」という今回のテーマとの関係は少しわかりにくいが、おそらく両者を繋ぐ概念は、「メディア」だと推察する。サイバネティック・アバターによって、遠隔操作と複数の作業の同時実現が可能なのは、行為者とそれが対象とする「現実」との間に、仮想空間の自分のアバターをはじめとした多くの媒介項が介在することにもとづいている。この媒介性を表わすことばが「メディア」である。
「メディア」という概念を歴史的にみたとき、その語源であるラテン語形容詞mediusや名詞mediumは、中間、中心、中途などを基本的な意味として、そこからさまざまな場面で中間として表象される事象に用いられるようになった。このラテン語をそのまま取り入れた英語においても、事情は同様である。そして「メディアコミュニケーション」に含まれる「メディア」の意味に近い用法の最初期の用例は、OEDなどによれば、フランシス・ベーコンの『学問の進歩』(1605)の言葉(ii.xvi. 2 “But yet is not of necessitie that Cogitations bee expressed by the Medium of Wordes.”)である。ベーコンは、伝達の道具として、話すこと(speech)と書くこと(wirting)を挙げ、またアリストテレスの言語論を(批判的に)引用しつつ、思考が必ずしも言葉(words)というmediumによって表現されるわけではないことを主張している。
この語源的探索は、ベーコンのこの議論を媒介として、mediumをめぐる考察が古代の哲学者たちの思考へとさらに遡源できることを示唆する。事実プラトンやアリストテレスは、伝達の媒体の性格や役割、人間の思考との関係に注意を払った。とりわけプラトンは、以上のような意味でのメディアを、言わば文化の総体として理解した。そしてオーラルな文化からリテラルな文化への移行という媒体の変化を背景としつつ、この媒体が人間の生き方に包括的に、そしてある意味では「直接的に」かかわることの問題性を論じている。
こうした議論を出発点に、行為の主体と対象に介在するメディア、そしてそれと思考との関係について、通常のメディア史やメディア論史とは異なるかたちで話題を提供したい。
- ②喜多 千草「疑似ローカル・同期のプレゼンスとしてのCA」
CAは、テレプレゼンス(ミンスキー, 1980)、テレイグジスタンス(舘, 阿部, 1982)を淵源とする遠隔でのプレゼンス技術の流れの嫡流に属すると考えられる。また、第二次世界大戦中に遡る人間ー機械混成システムから、サイボーグにいたる問題関心とも深く関わる上に、メディアを介したコミュニケーションの観点からは、電気的なコミュニケーションがもたらした場所性の喪失や、多様な自己呈示を可能にするメディアといった論点群にも接続している。本講演では、そういった論点群の見取り図を示した上で、「疑似ローカル・同期のプレゼンスとしてのCA」と場との関係についての視点を提供する。
- ①中畑 正志「In medias res ──媒介者としての「メディア」を歴史的に考える(仮)」
- 登壇者
- 講師:中畑 正志 (京都大学 名誉教授)
- 講師:喜多 千草 (京都大学 教授)
- コメンテーター:久木田 水生(名古屋大学 准教授)
- コメンテーター:藤川 直也 (東京大学 准教授)
- オーガナイザー:呉羽 真 (山口大学 講師)
主催:ムーンショット型研究開発事業目標1「アバターを安全かつ信頼して利用できる社会の実現」(PM:新保史生,プロジェクトウェブサイト)、同「誰もが自在に活躍できるアバター共生社会の実現」(PM:石黒浩,プロジェクトウェブサイト)
*1: 本講演会は、日立財団2021年度(第53回)倉田奨励金「メディアコミュニケーションのリデザイン――〈身体性〉・〈言語〉・〈環境〉に着目した応用哲学的探究」(代表研究者:呉羽真)の支援の下、第1回(バーチャル美少女ねむ氏講演会)、第2回(鳴海拓志先生講演会)を開催しました。今回は、ムーンショット型研究開発事業目標1のプロジェクトの支援の下、サイバネティックアバターに関する諸問題を重点的に検討します。
*2: 「サイバネティック・アバター」とは、「身代わりとしてのロボットや3D映像等を示すアバターに加えて、人の身体的能力、認知能力及び知覚能力を拡張するICT技術やロボット技術を含む概念」です(内閣府ムーンショット型研究開発事業ウェブサイトより)。
お問い合わせ先:呉羽 真(kureha[at]yamaguchi-u.ac.jp)
第7回(2023年2月19日(日))
第7回は「ビデオゲームとの向き合い方」と題して、児童精神科医で若者のゲーム依存の治療に取り組まれている吉川徹様、eスポーツを主に発達障害のあるお子さんの社会進出のために活用している吉沢純生様、そしてeスポーツを高齢者の方々の福祉向上や世代間交流に利用することを試みている岩尾憲治様のお三方にご講演いただきます。また講演会の後に、参加者の皆様に実際にeスポーツを体験していただき、ビデオゲームとの向き合い方を考えるきっかけ作りの場を提供致したいと考えております。
- 日時:2023年2月19日(日曜日) 13時~16時
- 開催方法:オンライン配信(講演会のみ、Zoom webinarでの参加可)および現地開催(愛知県名古屋市天白区井の森町232-1アイコービル 2F「e-Studio」)
- イベント後援:edges
- 参加申し込み:登録リンク
- プログラム:
- 受付開始 12時45分
- 講演会1 吉川徹 様(児童精神科医、愛知県医療療院総合センター部長) 13時00分
- 講演会2 吉沢純生 様(一般社団法人日本福祉協議機構 人材組織開発部長) 13時15分
- 講演会3 岩尾憲治 様(上飯田福祉会館 館長) 13時30分
- 質疑応答 13時45分
- eスポーツ体験会 「ロケットリーグで遊ぼう!」 14時00分
- イベント終了 16時00分
- 講演タイトルと要旨
- 吉川徹:「デジタルゲームへの『嗜癖』について考える」
近年、精神医学の世界では、アルコールや薬物などの物質への依存と類似して、行動への嗜癖が生じると考えられるようになっています。行動嗜癖の中で、もっともよく研究されているのはギャンブルへの嗜癖ですが、最近ではデジタルゲームに対しても嗜癖が生じるのではないかと考えられるようになっています。今回は長時間のゲーム使用などがみられる困難な状況にある子どもや若者への支援の際に、それを嗜癖とみなして支援することの功罪について、考えてみたいと思います。
- 吉沢純生:「デジタルツールと若者の未来」
近年、引きこもりや不登校といった日常生活に困難さを抱える児童が増加しています。こうした児童のなかには、自閉スペクトラム症(主に発達障害)の諸特徴が一般的な児童よりも比較的強い傾向にある児童が一定数存在しており、発達障害の診断の有無によって社会とのつながりを閉ざされてしまっているケースも少なくありません。また、Z世代(1996~2010年頃に生まれた10代前半から20代半ばの世代)やα世代(2010~2020年代頃に生まれた12歳以下の世代)にあたる児童は、e-sports、SNS、アプリ、配信動画といったデジタルツールが生活の中に当たり前に存在しており、性別や人種などに対する多様な価値観を認めているため、従来とは異なる学び方に柔軟で、興味関心や趣味を共有できる仲間とインターネット上でつながることも難しくありません。若者の未来について、未だ検討していない軸への気づきが得られる対話の機会となることを期待しています。
- 岩尾憲治:「eスポーツと高齢者福祉」
上飯田福祉会館は、市内在住の60歳以上の方を対象に、健康の増進、教養の向上及びレクリエーション活動、認知症予防・介護予防の取り組み等を実施しています。 令和4年度から始めた「eスポーツ」の体験者数は、8ヶ月間で述べ888名になりました。同好会も3つ立ち上がり、テレビゲームに馴染みのない高齢者世代に新しいコミュニケーションツールとして広がりつつあります。 また、児童館の子どもたちとの世代間交流における新たなコンテンツとしても注目しています。 本発表では上飯田福祉会館の取り組みを事例報告し、eスポーツの可能性について考えてみたいと思います。
- 吉川徹:「デジタルゲームへの『嗜癖』について考える」
- 講演者紹介
- 吉川徹 様:児童精神科医。愛知県医療療育総合センター 中央病院子どものこころ科(児童精神科)部長。あいち発達障害者支援センター副センター長。ほかにNPO法人日本ペアレント・メンター研究会副理事長、日本児童青年精神医学会代議員などを担当。愛知県を中心に発達障害のある児童青年の臨床に長年携わっている。
- 吉沢純生 様:一般社団法人日本福祉協議機構 人材組織開発部長/bring up株式会社 取締役/2022年名古屋工業大学大学院工学研究科博士前期課程工学専攻社会人イノベーションコース在学。
- 岩尾憲治 様:名古屋市上飯田福祉会館 館長。2008年 特定非営利活動法人かくれんぼに入職、2021年4月より現職。
第6回(2022年7月31日(日))
第6回は「アバター共生社会における身体性とコミュニケーション」と題して、認知科学者の岡田美智男先生(豊橋技術科学大学)と、倫理学者の水谷雅彦先生(京都大学名誉教授)のお二方にご講演いただきます。
- 日時:2022年7月31日(日)14時から
- 開催方法:対面とオンライン配信(Zoom webinar)のハイブリッド*
- 会場:名古屋大学東山キャンパス,全学教育棟SIS4(キャンパスマップ)
- 参加申し込み:登録リンク(参加者を把握するため、会場にお越しの方も登録をお願いいたします)
- プログラム(暫定):
- 14:00-15:30 岡田美智男先生講演(質疑応答含む)
- 15:30-17:00 水谷雅彦先生講演(質疑応答含む)
- 講演タイトルと要旨
- 岡田美智男:「〈弱いロボット〉研究の目指すもの」
「身体性って?」「コミュニケーションにおける身体の役割とは?」「ロボットを使ってコミュニケーションの研究を行えないものか?」というわけで、まったくの素人ながら、ここ25年近く、いろいろなロボットたちと関わってきました。また、意外にもポンコツなロボットが子どもたちの優しさや強みを引きだしていたなど、様々な偶然にも助けられて〈弱いロボット〉の概念が生まれ、育ってきました。本講演では、拙著『ロボット ― 共生に向けたインタラクション』(東京大学出版会)の概要を紹介するとともに、〈弱いロボット〉研究のこれからについても考えてみたいと思います。
- 水谷雅彦:「「アバター共生社会」の一歩手前の二話」
「アバター共生社会の倫理」という極めて興味深い論題の手前で考えておくべきことがいくつかあるように思われる。まず、前回の呉羽、木村両氏の報告にあった「対面神話/ 対面信仰」という妥当な指摘に屋上屋を架す形で、バーチャルリアリティにおける「劣化問題」を、理論的(事実的)劣化と実践的(価値的)劣化の区別をした上で、「リアル」とVRの差異を相対化してみる[1]。次に、にもかかわらず、現在のVRに物足りないものがあるのは、VRにとっての原理的問題であるというよりは、それが前提にしているコミュニケーション観に難点があるからではないかという指摘を行う。これは、哲学を始めとするコミュニケーション理論の多くが、未だにコミュニケーションを「半二重通信」の如きものとして扱っているために、通常の対面的コミュニケーションが「全二重通信」であるがゆえにもっている特性を捉えそこなっていることに起因する。アバター「共在」社会の構築にあたっては、まずこのようなコミュニケーションの「伝達モデル」を脱することが肝要であると思われる[2]。
[1] 「バーチャルリアリティは『悪』か」日本哲学会『哲學』第60号、2009.
[2]『共に在ること:会話と社交の倫理学』岩波書店、2022.
- 岡田美智男:「〈弱いロボット〉研究の目指すもの」
- 講演者紹介
- 岡田美智男先生: 豊橋技術科学大学 情報・知能工学系教授。1987年東北大学大学院工学研究科情報工学専攻博士後期課程修了、同年NTT基礎研究所情報科学研究部、国際電気通信基礎技術研究所(ATR)などを経て、2006年より現職。専門分野は、コミュニケーションの認知科学、社会的ロボティクス、ヒューマン・ロボットインタラクションなど。主な著書に、『ロボット 共生にむけたインタラクション』(東京大学出版会)、『〈弱いロボット〉の思考 わたし・身体・コミュニケーション』(講談社現代新書)、『弱いロボット』(医学書院)など
- 水谷雅彦先生:独立研究者、京都大学名誉教授。1957年生まれ。京都大学文学部卒業。神戸大学国際文化学部、京都大学文学研究科勤務を経て、2022年に定年退職。著書に、要旨に記した『共に在ること』のほか、『情報倫理学』(丸善)などがある。専門は倫理学、コミュニケーション論。
*感染拡大を防ぐため人数制限を行う場合があります。あらかじめご了承ください。
第5回(2022年6月12日(日))
第5回は「アバター共生社会のコミュニケーション」と題して、人類学者の木村大治先生(京都大学名誉教授)と、哲学者の呉羽真先生(山口大学)のお二方にご講演いただきます。
- 日時:2022年6月12日(日)14時から
- 開催方法:オンライン配信(Zoom webinar)
- 参加申し込み:登録リンク
- プログラム(暫定):
- 14:00-15:30 呉羽真先生講演(質疑応答含む)
- 15:30-17:00 木村大治先生講演(質疑応答含む)
- 講演タイトルと要旨
- 呉羽真:「コロナの時代の愛その他の人間関係について ――コミュニケーションメディアの技術哲学」
本講演は、遠隔操作型対話ロボットを含むコミュニケーションメディアの影響と倫理について、技術哲学の観点から論じる。コロナ禍では、感染拡大対策としてソーシャルディスタンシング戦略が採られ、対面コミュニケーションがテレビ会議等のオンラインコミュニケーションに置き換わる中で、「オンラインコミュニケーションは身体性に欠けており、対面コミュニケーションに質の面で劣る」といった言説が世間に流布した。講演者はコロナ禍の到来以前からコミュニケーションメディアの影響と倫理について研究を行っており[1][2][3]、その中で当該の言説を「対面神話」[2]と呼んで批判してきた。また、その過程で、以下のことを明らかにしてきた。
技術が社会に及ぼす影響は、技術それ自体の特性によっては決まらず、その技術が埋め込まれた社会のあり方に依存する。コミュニケーションメディア(スマートフォンやテレビ会議システム)が人間関係を貧困化させる、といった言説は、こうした技術と社会の関係を見落とす的外れなものである。
オンラインコミュニケーションが時として不適切になるのは、コミュニケーションメディアそれ自体の特性(情報伝達性能等)ではなく、オンラインコミュニケーションを選択する行為がその文脈に応じて担う「メタメッセージ」のためである。また、対面コミュニケーションが有する価値の一部は、それがその非効率性ゆえに担うメタメッセージに由来する。
オンラインコミュニケーションを脱身体化されているとする見解は、ある種の身体性を特権化する偏見に基づく。実際には、オンラインコミュニケーションも、対面コミュニケーションに見られるそれとは異なるものの、固有の身体性を有している。また、コミュニケーションの質を評価する上では、コミュニケーション主体の「身体多様性(somato-diversity)」を考慮に入れる必要がある。
本講演では、こうした講演者のこれまでの研究成果を紹介しながら、コロナ禍におけるソーシャルディスタンシング戦略が人間関係に及ぼした影響や、コミュニケーションメディアの心理学の知見を踏まえて、遠隔操作型対話ロボットの社会実装に向けたコミュニケーション観の刷新の必要性を説く。
謝辞:本研究は、日立財団 2021年度(第53回)倉田奨励金による課題「メディアコミュニケーションのリデザイン――〈身体性〉・〈言語〉・〈環境〉に着目した応用哲学的探究」(代表研究者: 呉羽真)の助成を受けたものです。
[1] 呉羽真 2020. 「テレプレゼンス技術は人間関係を貧困にするか? ――コミュニケーションメディアの技術哲学」, 『Contemporary and Applied Philosophy』11: 58-76. DOI: 10.14989/246427
[2] 呉羽真 2021. 「コロナ禍における大学授業のオンライン化は何を示したか? ――コミュニケーションメディアの技術哲学Ⅱ」, 『現象学年報』37: 107-113.
[3] 呉羽真 forthcoming(2022年6月初旬刊行予定). 「オンラインの身体性」, 『認知科学』29(2).
- 木村大治:「非対面性と共在感覚」
われわれはコロナ下で,対面性に関して考える機会が多くなった。そこではしばしば,「対面的なコミュニケーションこそが『本来の』コミュニケーションであって,非対面的なコミュニケーションはある種『非人間的』である」といった言説が見られる。私はこういった傾向を「対面信仰」と呼んで批判してきたが(木村 2020),この語は期せずして,今回のもう一人の講演者である呉羽真氏の「対面神話」とほぼ同一であった。その意味で,私自身の見解は呉羽氏のそれと大きく重なるのだが,同じことを話しても面白くないので,本日は独自の話題として,人類学のフィールドワークから見出された「視覚中心主義批判」と,コミュニケーション論における「コードモデル批判」について述べてみたい。
人類学者はフィールドにおいて,さまざまな「変な」コミュニケーションに出会う。今回はその例として,アフリカの農耕民ボンガンドと狩猟採集民バカの非対面的な音声コミュニケーションの事例を提示するが,この「変さ」を通じて,われわれは自分たちのやり方に関する相対化へと至るのである。
たしかに,対面的なコミュニケーションは,音声のみによる,か細いコミュニケーションよりも情報量的にリッチである。しかし,情報量の多さは「一緒にいる」という感覚(私は「共在感覚」と呼んでいる)とイコールなのだろうか?このことを考えるためには,シャノン流の「コードモデル」の再検討が必要であり,講演ではそれに代わる描像として,「くびれた風船モデル」(木村 2003)を提示してみたい。
木村大治 2003 『共在感覚 -アフリカの二つの社会における言語的相互行為から』326pp. 京都大学学術出版会。
木村大治 2020 「対面信仰」『TURN JOURNAL』 AUTUMN 2020 ISSUE 05 p.8, 公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京 p.8。
- 呉羽真:「コロナの時代の愛その他の人間関係について ――コミュニケーションメディアの技術哲学」
- 講演者紹介
- 木村大治先生:フリー研究者,京都大学名誉教授。1960年生まれ。京都大学大学院理学研究科博士課程修了,理学博士。京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科勤務を経て,2020年に早期退職。著書に,要旨に記した『共在感覚』のほか,『括弧の意味論』(NTT出版,2011年),『見知らぬものと出会う -ファースト・コンタクトの相互行為論』(東京大学出版会,2018年)などがある。専門は人類学,コミュニケーション論。
- 呉羽真先生:山口大学国際総合科学部講師。1983年生まれ。京都大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。大阪大学大学院基礎工学研究科知能ロボット学研究室(石黒浩研究室)等での勤務を経て、現職。著書に『宇宙倫理学』(共編著、昭和堂、2018年)、『人工知能と人間・社会』(共著、勁草書房、2020年)、『宇宙開発をみんなで考えよう』(共編著、名古屋大学出版局、2022年6~7月刊行予定)、など。訳書にアンディ・クラーク『生まれながらのサイボーグ』(共訳、春秋社、2015年)。専門は、科学哲学(特に認知科学の哲学、AI駆動科学の哲学)、技術哲学(特にコミュニケーションメディアの技術哲学)、応用倫理学(特にロボット倫理、宇宙倫理)など。
第4回(2022年4月24日(日))
第4回は「パラコンシステントな社会」と題して、大西琢朗先生(京都大学)と、永徳真一郎先生(NTT)のお二方に、デジタルツインコンピューティングにおける人のデジタルツインの在り方についてご講演いただきます。
- 日時:2022年4月24日(日)14時から
- 開催方法:対面とオンライン配信(Zoom webinar)のハイブリッド*
- 会場:TKPガーデンシティ京都タワーホテル 9F 紅花
- 参加申し込み:登録リンク(参加者を把握するため、会場にお越しの方も登録をお願いいたします)
- プログラム(暫定):
- 14:00-15:30 大西琢朗先生講演(質疑応答含む)
- 15:30-17:00 永徳真一郎先生講演(質疑応答含む)
- 講演タイトルと要旨
- 大西琢朗:「デジタルツインについての形而上学的・論理学的研究」
本発表では、発表者が参加しているNTTとの共同研究からのいわば「スピンオフ」としてスタートした、デジタルツインについての哲学的論理学的研究について紹介する。NTTとの共同研究は、デジタルツインについての技術的、実用的、ないしELISI的な(地に足のついた)検討を行うものであるのに対し、本研究ではそれらから距離を置いて、デジタルツインにインスパイアされた形而上学的ないし論理学的な(足元のおぼつかない)問題を追求している。トピックは(1) Logic of Alternative-Iと(2) Logic of Presenceの2つである。
(1) Logic of Alternative-I: 私たちは自身のさまざまなあり方、すなわち「可能な私」について考える。(人の)デジタルツインはこの「可能な私」が、想像上のものではなく、この現実世界に現れたものと考えることができるが、それはいったいどのような状況なのだろうか。いやそもそも「可能な私」とは何なのだろうか。ここでは「possibilia (可能的対象)」についての従来の形而上学説を踏まえつつ、N. Belnapの時制論理およびそれに基づくSTIT (see to it that)の意味論を利用して、「alternative-I」、すなわち意思決定の文脈で考慮される「可能な私」の論理構築を試みる。
(2) Logic of Presence: デジタルツインは完全に現実でもなく、かといって完全に非現実ないし反事実でもない、中間的な様相ステイタスをもつ存在者である。そのようなステイタスを本研究では「現前(present)」と呼び、さらに、あるエージェントが(別のエージェントにとって)現前していることを、それらの間に「相互志向性」が成立していること、と特徴づける。そのうえで、G.プリーストの「様相マイノング主義的志向性理論」を拡張し、「共有知識の論理」の枠組みを援用しつつ、相互志向性=現前性の論理を定式化する。
(本発表は、出口康夫・八木沢敬・秋吉亮太・白川晋太郎・山森真衣子との共同研究の成果である。)
- 永徳真一郎:「人のデジタルツインの位置づけに関する考察」
近年、実世界の人や物体をサイバー空間上へ写像、表現したものである「デジタルツイン」が実現されつつある。このデジタルツインの中でも、特に人のデジタルツインにおいて、人の外面だけにとどまらず内面をも再現できることによって、デジタルツインによる代理やデジタルツインとの共創など、人の機会と可能性は大きく広がると考えられる。一方、そのような人のデジタルツインは私や他者にとってどのような存在になり、また、そのためにはどのような要素が必要なのであろうか。
本研究では、京都大学 出口康夫先生、大西琢朗先生と共に、哲学的観点からこの考察を進めている。本研究において検討を進める中で、私のデジタルツインに対して私を認める観点として、機能的側面による類似性(機能的な私:Functional I)と、私とデジタルツインとの関係性(指標的な私:Indexical I)の2つの側面から、私のデジタルツインに私を認める可能性を整理している。本講演では、この考察の詳細について述べる。
- 大西琢朗:「デジタルツインについての形而上学的・論理学的研究」
- 講演者紹介
- 大西琢朗先生:京都大学大学院文学研究科特定准教授。2012年京都大学大学院文学研究科博士課程修了。博士(文学)。著書に『3STEPシリーズ論理学』(昭和堂、2021年)、訳書にイアン・ハッキング『数学はなぜ哲学の問題になるのか』(金子洋之との共訳、森北出版、2017年)など。京都大学オンライン公開講義「立ち止まって、考える」では運営・配信を務める。
- 永徳真一郎先生:NTTデジタルツインコンピューティング研究センタ 主任研究員。2006年 日本電信電話株式会社入社。バーチャルリアリティ、ヒューマンインタフェースなど、コンピュータと人の関係に関わる研究開発に従事し、現在に至る。博士(情報理工学)。現在は、デジタルのもう1人の自分である「Another Me」の実現にチャレンジするとともに、その社会的なありかたについても検討を進めている。
*当日の技術的なトラブルで配信できない可能性もあります。あらかじめご了承ください。
第3回(2022年1月30日(日))
第3回はバーチャルYouTuberに代表されるアバターを利用する際の問題点とその解決可能性に関して、分析美学とポピュラーカルチャーの哲学を研究されている難波優輝先生と、法学者の原田伸一朗先生(静岡大学)のお二方にご講演いただきます。
- 日時:2022年1月30日(日)15時から
- 会場:オンライン(Zoom meetingを使用)
- 参加申し込み:https://zoom.us/meeting/register/tJUtd-isqT8iEtVA_dzOOkLYgd6j1RmRgSTu
- プログラム(暫定):
- 15:00-16:30 難波優輝先生講演(質疑応答含む)
- 16:30-18:00 原田伸一朗先生講演(質疑応答含む)
- 講演タイトルと要旨
- 難波優輝:「"わたし"に触れるな - バーチャルなアバターに対する危害行為は中の人をどう傷つけうるのか?」
VRChatでアバターに対して性的な加害行為のような行為が行われる。
バーチャルYouTuberに対して誹謗中傷に類する行為が行われる。
これらは性的な加害行為なのだろうか、誹謗中傷なのだろうか? それとも、性的な加害行為のフリに過ぎないのか? 虚構のキャラクタに対する罵詈雑言のフリに過ぎないのか?
仮想空間と現実空間とを問わず、アバターに対してなされる行為は、いつ、そのアバターを操作する中の人を傷つけるのだろうか? 本発表はこの問いを扱う。特に、この問いに答えるためには何を考えなければならないのか、倫理学と美学の観点から明確化することを目指す。
ビジネス的な関心はこうだ。現在、Facebookがメタ・プラットフォームズに社名変更し、メタバース環境の構築を目指す事例に代表されるように、インターネットの次のプラットフォームづくりとして、メタバース構築に参入する企業が増えることは間違いない。そこで、運営するプラットフォームで倫理的な問題が起こった際に前もって対処できるような倫理的ルールづくりを行うことは企業にとって価値があるだろうし、ユーザーの利益を考える際にも重要になるだろう。また、やや特殊な業種にはなるが、エンタテイメント分野において、バーチャルYouTuber事務所がどのように所属タレントを保護するかについてもエンタテイメント法実務の観点からも若干の示唆を与えうるだろう。
学術的な関心はこうだ。バーチャル環境における行為や、バーチャルYouTuberに対する発言のように、純粋に虚構的世界でなされるわけでも、純粋に現実世界でなされるとも言えない微妙なステータスを持つ行為の倫理性について考えることは、倫理学と美学の道具を用いて現実世界の問題をどう整理できるかが試される応用哲学的なトピックだ。こうしたトピックを説得的に扱えるかによって、倫理学や美学が法学やビジネスにおけるルール策定にどう関われるかが問われる。
発表内容の予定としては、以下になる。Jeff Dunnが2012年にバーチャル環境における行為の道徳性を、同意、アバターとの同一化、遊びへの寄与という観点から論じている。このうち、アバターとの同一化に焦点を当て、分析美学におけるメイクビリーヴ・ゲームに関係する議論から、どのようなときに、どのような仕方でアバターとその中の人とが「同一化」しうるのか、図式を提示する。そこから、どのようなしかたで同一化がなされているアバターに対する危害行為がいわばアバターを貫通して中の人にまで危害を加えられるのか、哲学的再構成を行い、VRChatでの性的加害行為やバーチャルYouTuberへの誹謗中傷が一般的な意味で成立することを正当化してみる。
- 原田伸一朗:「VTuber法:バーチャルYouTuberの法的地位および人格権の保障」
バーチャルYouTuberは、その草創期、専らアバターが動いたりしゃべったりする技術として注目された。「人格」の分割・融合・拡張を可能にする未来技術の先行例として語られたりもする。しかし、VTuberは、単なるアバター技術として語られるにはとどまらない「文化現象」ともなっている。特に「中の人(配信者)」と「リスナー(視聴者)」との関係性・コミュニケーションを中核に、独特の「コミュニティ」が形成されていることは見逃せない。VTuberは、当初それを「キャラクター」とみなす傾向も強かったが、その「人格」や「身体性」はいまや無視できない要素となっている。このことが今後のアバター社会の法や倫理に示唆するところは大きい。
アバターに係る法的権利の保障や、それが活動する「メタバース」のルール形成が必要であることはすでに言われているが、スローガンにとどめず、未来社会において発生し得る問題を予測し、それに対応できる具体的な法律論(問題予測法学)を展開しなければならない段階に来ている。ムーンショットが想像=創造する未来と、VTuberの展開が必ずしも重なるとは限らないが、アバター共生社会の到来を見据えて、差し当たり現在のVTuber界隈においてどのような法的課題が生じているか、現行の法律論がどこまで適用できるか、足元を確認する機会としたい。
- 難波優輝:「"わたし"に触れるな - バーチャルなアバターに対する危害行為は中の人をどう傷つけうるのか?」
- 講演者紹介
- 難波優輝先生:1994年生まれ。美学者、批評家、SF研究者。修士(文学、神戸大学)。専門は分析美学とポピュラーカルチャーの哲学(バーチャルYouTuberとSF)。最近の著作に『SFプロトタイピング』(共編著、早川書房、2021年)、『ポルノグラフィの何がわるいのか』(修士論文)、「SFの未来予測はつねに間違っていて、だから正しい」(『UNLEASH』、2021年)、「キャラクタの前で」(草野原々『大絶滅恐竜タイムウォーズ』解説)。短編に『異常論文』収録「『多元宇宙的絶滅主義』と絶滅の遅延」(早川書房)。『ユリイカ』『フィルカル』『ヱクリヲ』『SFマガジン』などに寄稿。
- 原田伸一朗先生:静岡大学学術院情報学領域准教授。東京大学法学部卒業。筑波大学大学院図書館情報メディア研究科博士後期課程修了。博士(情報学)。同志社大学法学部任期付助教(有期)、静岡大学情報学部・大学院情報学研究科講師を経て現職。専門は情報法、コンテンツ法。
第2回(2021年12月2日(木))
第2回は「ゲーム依存・ビデオゲーム倫理の研究会」と題して、ゲーム依存症・ネット依存症の治療に取り組まれている藤原広臨先生(京都大学)と、eスポーツをはじめとするビデオゲームの倫理を研究されている岡本慎平先生(広島大学)のお二方にご講演いただきます。
- 日時:2021年12月2日(木)14時から
- 会場:オンライン(Zoom meetingを使用)
- 参加申し込み:https://zoom.us/meeting/register/tJcrcu6srDkjG9K2eObeoT3o-zL7cy5ldncj
- プログラム(暫定):
- 14:00-15:30 藤原広臨先生講演(質疑応答含む)
- 15:30-17:00 岡本慎平先生講演(質疑応答含む)
- 講演タイトルと要旨
- 藤原広臨:「良くも悪くも生活行動は健康に影響?:ほどよいインターネット使用・メディアマルチタスキングについての脳画像研究から」
生活習慣が脳構造・機能に影響することに関することについての知見が蓄積してきていますが、では、どの程度の生活行動が最適なのか?逆にいき過ぎると「行動嗜癖(物質に拠らない依存症)」として有害事象を引き起こすのか?については詳しくは調べられていません。本発表では、行動嗜癖に関する先行研究を踏まえつつ、現代に特有なインターネット使用や、それを前提・背景としたメディアマルチタスキングの程度が、意欲や注意力にどのように影響するのかについて、特に、より日常的・過度ではないレベルのこれらへのエンゲージメントの脳・認知機能への影響についての発表者らの成果についてご紹介するとともに、今後のこれらの生活行動に関する関わりについての意見交換に資するものとしたく考えております。
- 岡本慎平:「楽しいゲームが害になる時:インターネット・ゲーム障害の倫理的含意について」
ビデオゲームやそれを競技化したeスポーツのプレイ人口が増加し、市場規模が大きくなるにつれ、ビデオゲームがプレイヤーにもたらす正負両面での影響が議論の的になる機会が増えている。一方で、ビデオゲームの優れたプレイは諸々の能力の卓越として理解されるようになり、認知症予防などのポジティブな効果も実証されつつある。他方で、インベーダーゲームやファミコンの時代より、ビデオゲームは様々な悪影響をもたらすと論難されてきた。とりわけビデオゲームのもつ依存性は「インターネット・ゲーム障害(IGD)」と呼ばれ、近年では、例えばキング&デルファブロの『ゲーム障害:ゲーム依存の理解と治療』(福村出版、2020年)に代表される経験的データの蓄積も増えている。もちろんビデオゲームのプレイとこれらの症例の間にある因果関係は未確定の部分が大きいとはいえ、IGDにより社会生活に支障をきたす患者が実際に存在すること自体に疑いの余地はない。だがそれを理由にして、公的な規制や業界への政治的介入をおこなうことはどの程度倫理的に正当なのだろうか。本発表では、公衆衛生倫理の観点から、IGDが規制や介入の理由になりうるかどうか、そしてもし一定の理由になるとすれば、どのような対処を正当化しうるのかを検討する。
- 藤原広臨:「良くも悪くも生活行動は健康に影響?:ほどよいインターネット使用・メディアマルチタスキングについての脳画像研究から」
- 講演者紹介
- 藤原広臨先生:M.D. Ph.D. 京都大学大学院医学研究科 脳病態生理学講座(精神医学)講師、理化学研究所 革新知能統合研究センター 人工知能倫理・社会チーム 客員研究員
- 岡本慎平先生:Ph.D. 広島大学大学院文学研究科 応用哲学・古典学講座 倫理学研究室 助教
第1回(2021年11月14日(日))
漫画家の山田胡瓜先生をゲストにお招きしてご講演いただきます。ご講演の後は、石黒浩先生、大澤博隆先生、中野有紀子先生、新保史生先生にご登壇いただき、パネルディスカッションを行います。最後に、参加者をまじえて「市民対話*」を行います。
- 日時:2021年11月14日(日)14時から
- 会場:オンライン(Zoom Webinarを使用)
- 参加申し込み:https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_xeHtJB49SOSrdQhF5Kt0aA
- プログラム:
- 14:00- 趣旨説明
- 14:05-15:00 第1部:山田胡瓜先生講演
- 15:10-16:00 第2部:パネルディスカッション
- 16:10-17:00 第3部:市民対話
- 講演タイトルと概要
- 「SF漫画的想像力で考えるアバター社会」
- 「バイナリ畑でつかまえて」「AIの遺電子」など、テクノロジーと人間の関わりを描いてきた漫画家が「アバター社会」について考えたことを話します。
- 山田胡瓜先生プロフィール:IT記者としての活動の傍ら作品を書き続け、2012年、『勉強ロック』で「月刊アフタヌーン」アフタヌーン四季大賞を受賞。2013~2015年に「ITmedia PC USER」に連載した『バイナリ畑でつかまえて』で注目を集める。2015~2017年に「週刊少年チャンピオン」で連載された『AIの遺電子』は、人間そっくりのヒューマノイドを治療する医師を主人公にした、AIと人の関係を描く近未来SFコミックとして、各方面に大きな反響を呼び、2018年に第21回文化庁メディア芸術祭漫画部門優秀賞を受賞。2017~2019年には「別冊少年チャンピオン」にて『AIの遺電子RED QUEEN』を連載。2020年からは同誌にて『AIの遺電子 Blue Age』を連載中。
- 司会:久木田水生
*市民対話:Webinarの「パネリストに昇格」機能を用いて、一般参加者の方にもパネリストとして登壇いただいて、山田先生や他のパネリストの先生方と直接議論できる場を設けます(ビデオカメラをonにしなくても構いません)。登壇をご希望の方は登録フォームでお伝えください。なお、希望人数や職業・年齢の偏りを減らすなどの理由で、ご希望に沿えない場合もありますのでご容赦ください。もちろん、登壇を希望されない方からの先生方への質問も受け付けますので、登録フォームや当日のQ&Aにご記入ください。
本研究プロジェクトはJSTムーンショット型研究開発事業「誰もが自在に活躍できるアバター共生社会の実現」JP-MJMS2011の助成を受けています。